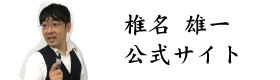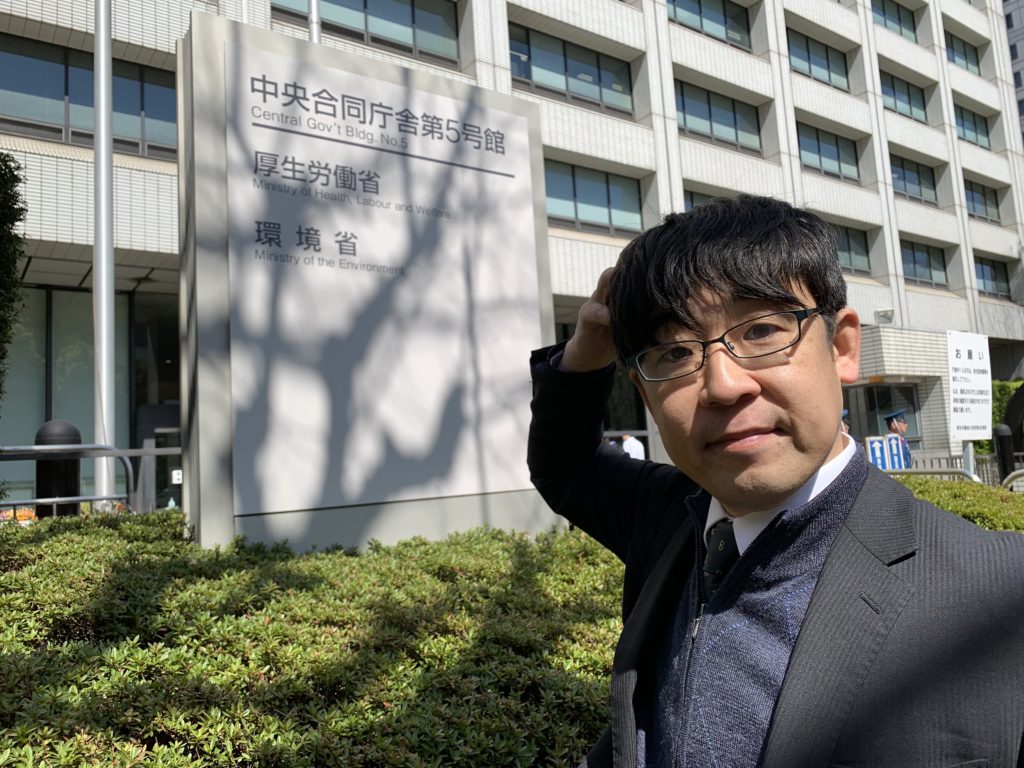厚生労働省@霞が関
農林水産省に引き続き、厚生労働省にいってきました。都会で居場所が見つからなかったり、役割が見えなかったり、部屋にこもっている人が増えている中でどこまでが国の範疇(公助)でどこからが私たちがともに助け合わないといけない範疇(共助)、そして、自分でやる範疇(自助)なのかを知るためです。

1.厚労省の建物
連日、霞ヶ関を訪れると省庁によって、ビルが違い、警備の仕方が違い、人の空気が違うのがよくわかる。農林水産省が「身体」だとしたら、厚生労働省は「頭」というような違いを感じた。ビルにも人の動きにもロジックを感じる。
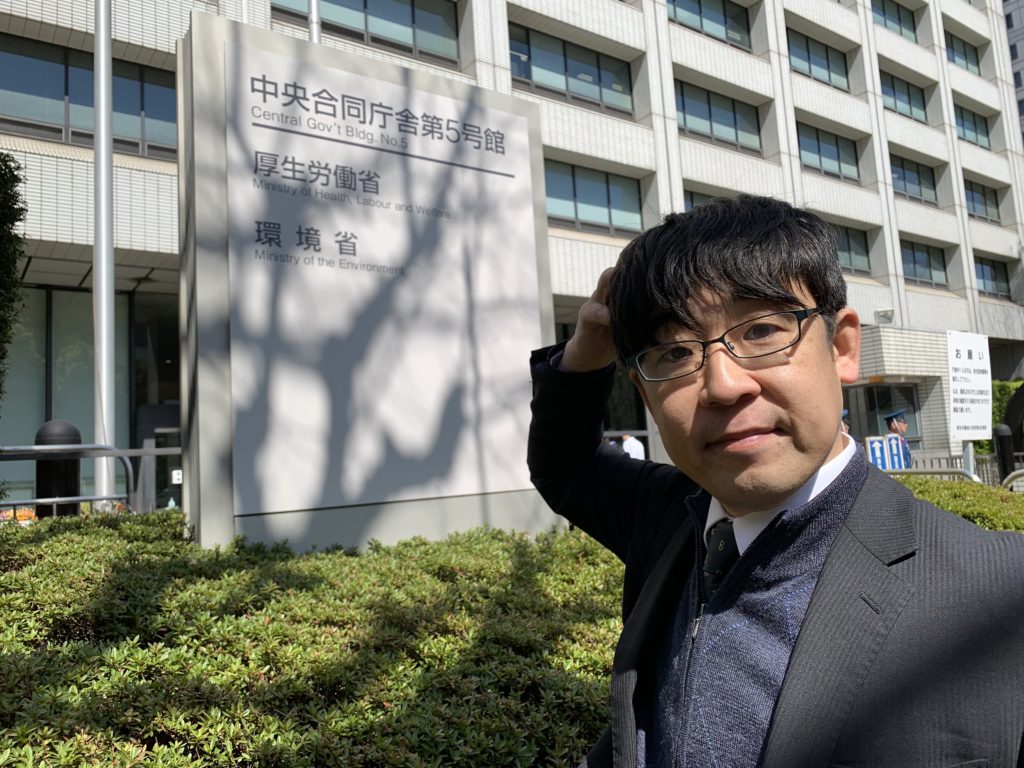
2.仕事の早さ
身元も高校の経営をしているくらいしか話していないにも関わらず、立ち話の内容をよく覚えていてくださって「仕事早い!」農林水産省の時と同様にあまり詳しいことはここでは書けないが、行政の仕組み(教科書的なのではなく、体質や攻略法(?))を具体的に教えていただいた。

3.三権分立
私は理系の出身なので特に社会科には疎いが、会話をしながら「三権分立」という懐かしい言葉を思い出した。「決定されたルール」に当てはめて運用するのが仕事なので、「当てはまるかどうかを判断する」「当てはまるならどれが適用できるかを判断する」という流れで話が進んでいく。
相談した内容で現行のルールに当てはまりそうなものについては具体的にアドバイスをいただくことができた。一方で創造的なアイディアに関してはその発想がどうこうではなく「現行のルールに当てはまらない」というのが結論のようだった。医療のモデルにとても似ている。
「発達障害」や「うつ病」のような概念もここ数年から十数年で一気に広まった。1990年代に精神科に通っていた私は「異常がない」という診断をいろいろな病院をまわって受け、1年くらいしてようやく「うつ」という単語に出会った。おそらく、その頃には多くの医師にとって「無い」概念だったのだろう。

4.臨機応変と杓子定規
打ち合わせが進むにつれて、厚生労働省の人との話し方に慣れてきた。「国」としての基準を踏まえていると言うことが言動レベルで理解できた感じだ。
ホワッとした感じでは理解できていたが明確に理解できたのが以下の2つ。あらためて
「社会科が弱いな」
政策に乗る
国だけではなく、都道府県や市区町村も総合戦略なりのビジョンを公表している。ひきこもりから経営者になった私としてはあまり関わってこなかった部分だ。疎いというよりあまり縁がなかった。
早速、各省庁の大臣の記者会見や各市区町村の総合戦略をチェックしたらどの行政と関わったら良いのかが見えてきた。
想定されていること
すでに決まっていること。想定されていること。計画されていることに関しては公助を得やすい。逆に想定されていないことは内容云々ではなく、公助は得にくい。確かに「オリジナルの住民票ください!」のような話は対応しにくいだろうと思う。
いわゆる民間の強みは「臨機応変」
それを支える行政は全体を見ているので決められた範囲内で「杓子定規」にならざるを得ない。これが「公助」と「共助」の境目なのだろう。

そんな基礎的なところから始まって、県の特性、市区町村のどの窓口に相談したら良いのか(どこだと対応してもらえないのか?正確に言い換えると対応する準備がある窓口なのかそうでないのか?)を具体的にアドバイスをもらった。具体的な市区町村や窓口がイメージできると一気に世界が広がった。
5.グレーゾーン
厚生労働省の方の話し方で特徴的だったのが、「基本的には困っている人全員が対象です」という言葉。一方で「実際に支援をするとなると優先順位があるので、障害が重い方を優先せざるを得ない」という。この2つがセットだ。
うつ病ひとつとってもうつ病の周辺の「軽症うつ病」「適応障害」とその周辺の症状で悩む人も少なくない。他の診断名もそうだ。「発達障害」などにも同じことが言える。グレーゾーンの人たちには「公助」は行き届かない。それらがむしろ「共助」の領域なのだと思う。グレーゾーンの人たちが元気になるには国の制度を活用しつつも柔軟に動ける企業などと提携するのが近道のようだ。
6.協力企業募集
大きな企業では休職中の人が多いが「病院任せでいっこうに回復しない」という声をよく聞く。「メンタル不全で休職にはいると社員が戻ってこない」ともいう。もし、企業がその社員に復活してほしいと願うなら、この活動を応援してほしい。
都会で消極的回復を図るよりも地方で再生するための体験をすることを企業が応援してくれれば本人の負担も少なく、企業のダメージも少なく、回復を図ることができそうだ。