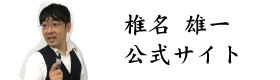傾聴講座@ユメソダテ 報告
どんな人でも夢を持っていきられる。障害者であっても、そうでなくても。そんな社会を生み出すために田園都市線の桜新町駅、桜神宮にてイベントが開催されました。
1.隔離と無理解
障害者は社会から見えにくいところで生活しています。元気な人は元気な人だけで成立する社会を好みます。力の強い人だけでチームを作って、そうでない人はいないかのようです。
そんな隔離、分離によって、私たちは障害者に触れる機会がありません。高齢者も精神的に病んでいる人もそうです。
社会が慣れていないから関わり方がわからない。
理解がないから対応できない。
そんなふうにオロオロしている人を見たら、申し訳ないと感じてしまう。だから、障害者は意見を言わない。夢を考えない。「施設で働くことが夢です」と言わせてしまう。

2.人の心のチカラ
人の心がバラバラな時に人は自分の仲間じゃない人を排除しようとします。仲間ということは仲間じゃない人がいるということ。
でも、人の心が同じ方向を向くと驚くべきパワーが発揮されます。
この会にはさまざまな人が「出店者」としても参加してくれました。
芸術家、パンケーキ屋さん、学校、親の会、子供食堂、企業などなど
中でも驚いたのが「高校3年生」
自分が作った、アクセサリーやバッグが誰かの笑顔になるならと初めて参加して出店してくれました。多くの悩んでいる人は「やってもらうがわ」から出ようとしません。でも、高校生でも自分の意思で「やるがわ」にまわることができます。その差は才能ではなく意識だと思います。
「やるがわ」にまわると世界が変わります。「やってもらうがわ」だったときに不満に思っていたことがいかに難しいか?「やってみる」ということで気づくことはたくさんあります。高校三年生でその壁を越えて、参加していることにまず驚きました。
3.ライブの傾聴講座
そんな場で傾聴講座をさせていただきました。
「傾聴とはこうですよ!」と伝えるのではなく、会場の人とリアルに会話をしながら、夢を聞いたり、思いを聞いたりしました。「聞き方」を教わるよりも「聞いている場面」を見たり「聞いてもらう体験」をすることにこそ傾聴講座の醍醐味があると私は思います。
そんな中でも上記のいろいろな団体の人にも話をしてもらいました。
夢についてアイディアが全くない人でも人の夢を聞けばひらめくことがあります。人の夢を応援することで自分の夢が叶ったり、見えてくることもあります。
4.1mmでも動こう
助けてもらうこと。やってもらうことに慣れている人は人にやらせておいて文句を言います。
毎日の食事を作ることはその食事にありがとうと言うより大変です。当たり前ですが。
毎日の食事を作ったら、ありがとうと言われてホッとします。無視やノーリアクションでは作った甲斐がありません。
こうして毎日作る人と食べるだけの人の差が生まれます。福祉も同じです。されっぱなしの人ほど文句を言うものです。だからこそ、1mmでいいから動こう。拍手ひとつ。ありがとうひとつでもいいからする側を体験しようとまとめました。