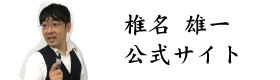福祉施設の食の仕事@精華学園高等学校
全日制の高等学校に通っていると国語算数理科社会英語を頑張るのが正しいように感じるかもしれない。でも、なぜ全日制の高校では国語算数理科社会英語なのだろう? と思うことがある。今回は生徒を連れて、福祉施設の厨房での仕事を見学してきた。
目次
1.国語算数理解社会英語に未来はない
素朴な疑問だが主要5科目を頑張っても未来は見えてこない。一般教養という意味では大事なのは理解しているけれども未来が見えるかというのは別だ。
「将来何に生かすかわからないのに勉強する」 この苦痛を生徒から感じることが多い。 国語算数理解社会英語がそのままの形で将来につながっていて、全員が記者、科学者、通訳になるわけではないからだ。
2.福祉施設で食事を作る
実際に生徒を連れて、2つの施設を見学させてもらった。 国語算数理科社会英語から見えてこないことが当然だけれどたくさんあった。
衛生管理
白衣、マスク、靴、手洗い・・・職場としては当然だけれど教室からは見えにくい衛生管理のピリピリ雰囲気を味わうことができた。1人1分かけて手を洗う。ブラシで爪の間の汚れも落とす。

調理方法 高齢者の施設では入居者ひとりひとりで食事が違う。食べ物の柔らかさやサイズ、薬との組み合わせで食べさせてはいけないものもある。個人名と注意事項を照らし合わせながら食事を用意する。
シフトと役割
早朝シフトの人がここまで作業をして、昼間のシフトの人がそれを引き継いで、野菜のカット専門の障害があるスタッフがいて、それで仕事がまわっている。学校ではあまり味わえない役割分担だ。
見慣れない機械
スチームで料理をする大型の機械や何十人分もの料理を一気に作る大型の鍋(かき混ぜやすい機能付き),一人では持ち上がらないくらい大きなまな板。人が入れる大きな冷凍庫。一気に食器が洗える大型の洗浄機。
それらが実際に稼働している様子を見ると迫力を感じるし、ワクワクしてくる。

入社間もない人
働き始めて2年目という人が職場の説明をしてくれた施設もあった。年齢が近い人がしっかりと業務を理解して、その業務の意味を理解して仕事をしている。

ふだん、保護者や電車で疲れた大人しか見ていない高校生には刺激的な関わりだ。
栄養の管理と献立
現場には調理師さんだけでなく、栄養士さんもいて栄養のバランスの良いメニューを考えて、献立を決め、発注をして、1日1日の作業工程を文書にして指示をしていた。

高齢者の食べられるものに応じて、何パターンかの食事を並行して作ってその組み合わせで規定の栄養バランスになるように配慮されている。これを毎日するのは大変なことだと思う。
人の顔
カウンターの向こう側には老人ホームに入居している高齢者がいる。食事をすませるとおぼんごとカウンターに持ってきてくれる。「全部食べてくれていると嬉しい」と厨房のみなさんは口を揃えて言う。実感がこもった言葉だ。
3.何をしたら良いか?
しつこいようだが 国語算数理科社会英語を頑張っていても「自分が社会で何をするべきなのか?」が見えてこない。 でも、 このように職場をじっくり(半日がかりだった)見学をして現場を見て、現場の声を聞けるとイメージが湧く。
「野菜を切る係なら慣れればできるかもしれない」
「この紙を見ながらなら調理も慣れれば、、、」
「手の洗い方は今日覚えた」
「何だできそうじゃないか!」
そう思ってくれると未来が見えてくる。
仮に国語算数理科社会英語ができなくてもこの現場で必要なことを覚えて、人と協力しあえれば役割があるのだ。
4.就職先に
見学した生徒たちはこの仕事に興味を持ったようで採用試験を受けることになった。
履歴書とスーツ
採用試験にはこれらが必要だが用意するのに2週間かかった。大人にとっての当たり前とこれから社会に出て行く若者の感覚は違う。慣れないことへの不安やしっかりとやりたいという思いもあるのだろうと思う。それでも現場を見て、イメージがしっかり湧いた生徒たちは教室で国語算数理科社会英語をやっていた時と様子が違う。
5.学校教育
役割が見えてくるとそれに足りないことは学びたくなる。スーツを買うことも調理に興味を持つこともそうだ。
先生自体も何の役に立つのかわからないまま授業をしている学校のスタイルは調べたら大正時代から大して変わっていない。
大正時代の電話機はとなりのトトロに出てくるような電話だ。それがスマホになっているくらい社会が変わっているのに学校は本当に古いままだなと思う。
生徒が興味を持った職種の現場を見せる。
これは現代の教育に欠かせないものだと思う。
学校が勝手に決めた社会人に講演をさせるのとはまったく違う。生徒が希望したものをテーマに現場を見ることが大事なのだ。業界の情報を知りたいのでもその大人の自慢話が聞きたいのでもなく、彼らは自分の居場所がそこにあるかを知りたいのだから。